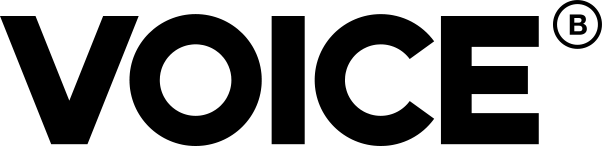ホームページ XXXIX
「クリニックのためのホームページ制作ガイド【2025年版】」
近年、クリニック選びにおいてホームページの重要性が急速に高まっています。
患者は来院前に必ずといっていいほどインターネットで情報を調べ、診療内容や雰囲気、医師の人柄を確認します。 その第一印象を左右するのが、クリニックの公式サイトです。
清潔感のあるデザインやわかりやすい導線はもちろん、
「どんな治療を行っているのか」「どんな考えの医師なのか」といった“信頼感”を伝える設計が求められます。
さらに、検索エンジンやSNSなどオンライン上の複数の経路から患者が流入する現在、
ホームページはクリニックの“オンライン受付窓口”としての役割も担っています。
この記事では、そんな時代におけるクリニックサイトの考え方と制作のポイントを、 実際の制作事例を交えながら解説します。
制作の方向性をイメージする際は、実際のWeb制作実績も参考になります。
▶︎Web制作実績はこちら
01 なぜ今、クリニックにホームページが必要なのか
クリニック向けホームページ制作の重要性
医療機関にとって、ホームページは患者が最初に出会う診療の入口です。
近年は「近くの小児科」「内科 口コミ」「夜間対応 クリニック」といった検索で来院先を決める人が増え、オンライン上の印象がそのまま信頼感につながるようになりました。
いまや、患者がクリニックを探すとき、最初に開くのは検索サイトや地図アプリといってもいいでしょう。「皮膚科 金沢市」「小児科 夜間」「整形外科 口コミ」など、条件を入力して比較検討するのが当たり前になりました。
その中で、オンライン上での存在感――つまりオンラインプレゼンスを確立しているかどうかが、患者の来院を左右します。
とくに2025年以降は、検索エンジンだけでなく生成AIによる情報参照も増えています。
つまり「Web上に正確で信頼できる情報があるかどうか」が、クリニックの“存在証明”ともいえるでしょう。
ここでは、患者獲得のためのホームページ制作で押さえるべき3つの要点を紹介します。
1. 地域に特化したSEO対策を行う
クリニックや医院の検索は「地域名+診療科」で行われることがほとんどです。
そのため、ホームページの構造や文中に地名と診療キーワード(例:金沢市 小児科/内科 診療)を自然に織り込むことが重要です。
Googleマップやローカルビジネス情報(Googleビジネスプロフィール)とも連携することで、近隣患者の目に触れる機会を増やせます。
地域に密着したSEO設計は、“近くの信頼できる医院”として選ばれる第一歩です。
2. モバイルフレンドリーなデザインを採用する
スマートフォンから診療時間を確認したり、予約ページにアクセスしたりする患者は年々増えています。
そのため、モバイル端末での見やすさ・使いやすさを前提に設計することが不可欠です。
文字の大きさ、ボタンの配置、地図や電話リンクの導線など、モバイル利用を中心に設計されたサイトは、閲覧者の離脱を防ぎ、予約や問い合わせの増加につながります。
3. SNSとの連携を強化する
院内からの情報発信を活発化させるうえで、SNSとの連携は大きな武器になります。
たとえば、Instagramで院内の雰囲気や小児科のイベントを紹介し、ホームページに埋め込むことで安心感と親しみやすさを同時に伝えることができます。
また、LINE公式アカウントやX(旧Twitter)を活用すれば、休診・診療時間変更などの告知もスムーズに行えます。
SNSを通じて院長や医師、スタッフの顔が見える発信を続けることが、患者との信頼関係の基礎になります。
信頼性を高めるための情報提供
□専門的なコンテンツを充実させる
患者がクリニックを選ぶ際に重視するのは、「自分の症状にきちんと対応してくれるか」という安心感です。
そのため、専門的な情報をわかりやすく整理したコンテンツが信頼構築の鍵になります。
たとえば、診療科ごとの治療方針、医師の専門領域、使用機器や検査方法などを丁寧に紹介することで、医療機関としての信頼性が高まります。
過剰に専門用語を並べるのではなく、一般の方にも理解できる言葉で説明することがポイントです。
□患者の声や症例紹介を掲載する
実際に治療を受けた患者の声や、症例紹介は“見えにくい実績を伝える資料”になります。
「どんな症状の方がどのように改善したのか」「どのような治療対応を行ったのか」を写真やグラフとともに掲載することで、初めて受診する人の不安を軽減できます。
また、スタッフ紹介や院内の雰囲気を伝える写真を追加することで、“人が見える医療機関”としての温かみも伝わります。
□定期的な更新を行う
医療情報は日々進化しており、古い情報がそのまま残っていると信頼性が低下します。
定期的にニュースやお知らせを更新し、診療時間の変更や季節ごとの健康情報などを発信することで、「このクリニックは今も活動的でしっかり対応している」という印象を与えられます。
更新を継続できる体制を制作段階から整えておくことが、長期的な信頼獲得の仕組みになります。
クリニックにおけるオンラインプレゼンスの必要性
□競合との差別化に役立つ
近年は、同じ診療科でも複数のクリニックが近距離に存在しています。
この中で選ばれるには、オンライン上での「違い」をどう伝えるかが鍵になります。
たとえば、
•皮膚科なら「女性医師による診療」「美容施術にも対応」
•小児科なら「オンライン受付」や「夜間診療」
•整形外科なら「リハビリ機器の充実」「スポーツ診療への対応」
といった特徴を明確に打ち出すことで、検索結果からのクリック率や予約率が上がります。
オンラインプレゼンスは、まさにデジタル時代の看板です。
□24時間アクセス可能で利便性が向上
ホームページやSNSは、24時間いつでも患者とつながる場所です。
診療時間外でもアクセスできることで、患者は自分の都合の良い時間に情報を確認できます。
特に、予約システムやオンライン問診を導入すれば、夜間でも受付や確認が可能になり、”時間に縛られない医療体験”を提供できます。
これは、忙しいビジネスパーソンや子育て世帯にとって大きな利点です。
02 クリニックホームページ制作の流れ
初期相談から公開までのステップ
クリニックのホームページ制作は、単なるデザイン業務ではなく、開業や運営の戦略と深くつながるプロジェクトです。
患者に信頼されるサイトをつくるためには、初期段階から目的を明確にし、スケジュールとフィードバック体制をしっかり整えることが欠かせません。
ここでは、初期相談から公開までの主なステップを紹介します。
1. 初期相談:目的と方向性を定める
制作の第一歩は初期相談(ヒアリング)です。
この段階で、
・どんな患者層に来院してほしいか
・どんな診療内容を強調したいか
・どんな印象を与えたいか
を明確にしておきます。
開業準備中のクリニックであれば、「開院日」「診療科目」「診療時間」「受付体制」「請求システム」など、運営情報も合わせて整理します。
目的を具体化することで、デザイン・構成・情報発信の方向性が定まり、制作後のブレを防ぐことができます。
2. スケジュールを設定して進行を可視化
クリニックの運営スケジュール(開院日・内覧会・新規受付開始など)に合わせ、制作のスケジュールを逆算して設計します。
たとえば、
•初期設計:4週間
•デザイン案提出:2〜3週間後
•内容確認と修正:2〜3週間
•サイト公開・登録作業:全体で約3ヶ月〜
といった流れで進行することが一般的です。
スケジュールを可視化しておくことで、開院準備や他の施策(SNS展開・広告出稿)との連携が取りやすくなります。
3. フィードバックを重視した制作プロセス
制作中は、定期的なフィードバックと確認が品質を左右します。
「思っていた印象と違う」「この診療科をもう少し目立たせたい」など、早い段階で修正を行うことで、完成度を高められます。
特に写真や文章の部分は、医療法や広告規制に配慮しながら制作会社と二人三脚で進めることが大切です。
このやりとりを丁寧に行うことで、公開後の運用もスムーズにサポートへつながる仕組みが整います。
4. 公開とアフターサポート
公開時は、Googleビジネスプロフィールの登録やアクセス解析ツールの導入など、オンライン上の受付体制を整える作業も必要です。
公開後も、更新代行や保守管理などのサポートを受けながら、必要に応じて情報を追加・改善していくことが理想的です。
クリニックの成長に合わせてWeb展開を強化していくことで、地域の患者との接点を継続的に広げられます。
デザインとコンテンツの重要性
クリニックのホームページは、デザインとコンテンツの質が信頼の第一印象を左右する要素です。
訪問者は数秒で「この医院は信頼できそうか」を判断します。
だからこそ、視覚的な安心感と、患者の知りたい内容を的確に伝える情報設計が欠かせません。
ここでは、デザインとコンテンツを両輪として捉えるためのポイントを紹介します。
□視覚的なインパクトを考慮する
クリニックのWebデザインでは、「清潔感」「安心感」「親しみやすさ」という印象が最も重要です。
たとえば、白や淡いグリーンを基調にした色設計、柔らかな照明の院内写真、医師やスタッフの笑顔など、“目に入る瞬間の安心感”を演出します。
トップページ(Top)には、医院の理念や診療科の案内をわかりやすく配置し、患者が迷わず目的のページにたどり着けるようにすることが理想的です。
デザインは単なる見た目ではなく、医療の信頼を伝えるビジュアル・コミュニケーションなのです。
□ユーザー目線でのコンテンツ作成
医療系サイトでは、閲覧者の多くが「不安」や「疑問」を抱えてアクセスします。
そのため、医療従事者が伝えたいことよりも、患者が知りたいことを中心に構成することが大切です。
たとえば、
•診療科別の症状案内(例:内科 → 発熱・倦怠感・生活習慣病)
•初診時の流れや持ち物
•治療後の連絡方法や再診の案内
など、患者が知りたい情報をシンプルに整理します。
また、定期的なブログ更新も効果的です。
季節の健康情報や予防のヒントなど、実用的な内容を発信することで、信頼とアクセスの両方を育てられます。
これが継続的なWeb運用=「デジタル版の待合室づくり」です。
□SEO対策を意識する
どれほど良い内容でも、検索されなければ患者に届きません。 検索エンジンで上位表示を目指すためには、キーワードを自然に含んだコンテンツ設計が重要です。 たとえば「金沢市 小児科」「内科 夜間診療」「皮膚科 女性医師」といった検索意図に沿ってページ構成を考えることで、アクセスが増加します。 また、各ページには「タイトル」「見出し」「画像の代替テキスト(alt属性)」を適切に設定し、検索ロボットにも内容が伝わるように設計します。 SEOは専門的なコンサルティングを受けることも効果的ですが、日々の情報更新やブログ投稿を継続することが最も実践的な対策です。
03 クリニックホームページ制作の費用相場
一般的な価格帯とその内訳
ホームページ制作を検討するとき、多くのクリニックが気になるのが「実際いくらかかるのか」という点です。
価格は制作会社やプラン内容によって幅がありますが、費用の目安や内訳を把握しておくことで、見積もり時に「何が高いのか」「どこまで含まれているのか」が分かりやすくなります。
□基本的な制作費用の目安
一般的なクリニックホームページ制作の相場は、50万円〜100万円程度が目安です。
ただし、デザインの自由度やページ数、機能の有無によって金額は変動します。
□デザインと機能の違いが価格に影響する
費用が高い/安いの違いは、単にデザインの見た目ではなく、
“どれだけの機能を持たせるか”にあります。
たとえば以下のような項目はオプション扱いになることが多く、費用が追加されます。
•オンライン予約・問診フォームの設置
•スマートフォン対応の最適化設計
•スライドバナーや動画を使ったトップ画像
•SEO分析やアクセス解析レポート機能の導入
•医療法に準拠した広告チェックサポート
これらを含めることで、患者の利便性を高めつつ、集患効果を可視化できるサイトに仕上がります。
□運用コストも忘れずに
ホームページは公開して終わりではなく、運用・保守の継続費用も考慮する必要があります。
サーバー管理やドメイン更新、セキュリティ対策、定期的な情報更新などを外部に依頼する場合、 月額10,000〜30,000円前後が一般的です。
また、ブログ投稿やお知らせ更新を代行してもらうプランでは、内容量に応じて月5万円程度になることもあります。
費用はかかりますが、定期更新はSEO効果を高め、長期的には集患につながる投資です。
□見積もり時のチェックポイント
見積もりを依頼する際は、「どこまでの作業が料金に含まれているか」を必ず確認しましょう。
撮影・ライティング・デザイン・コーディング・SEO設定など、項目ごとに明記された見積書であれば安心です。
「一見高いと思っていたけれど、サポート内容を考えると納得できた」というケースも多くあります。
総合的な視点でコストを分析し、“値段”ではなく“価値”で判断することが重要です。
□外注の際の注意点
費用を抑えたいからといって、安さだけで業者を選ぶのは避けましょう。
「とにかく安い業者」に依頼すると、セキュリティが弱かったり、修正対応が遅かったりといったトラブルが発生しやすくなります。
外注を検討する際は、次のポイントを確認しましょう。
•医療機関向けの制作実績があるか
•見積もり内に「修正対応」「サポート費用」が含まれているか
•公開後の保守や更新対応をどこまで任せられるか
信頼できる業者であれば、必要な費用と不要な費用を整理して提案してくれるため、結果的にコストを抑えながら安心して任せられます。
□長期的な視野での投資を考える
短期的に費用を抑えるだけではなく、長期的な運用コストと効果を意識することが重要です。
たとえば、初期費用を抑えたテンプレートサイトでも、更新やSEO対策を怠ると数年後には検索順位が下がり、結果的に再制作が必要になるケースもあります。
一方で、はじめからしっかり設計されたサイトは、5年、10年と安定した集患効果を持続します。
長期的に見れば、SEO対策・保守運用・情報更新といった投資は「コスト」ではなく「成果につながる基本戦略」といえるでしょう。
04 実績豊富な制作会社の紹介
クリニックの制作事例から見る信頼とデザインの両立
クリニックのホームページ制作では、単に見た目を整えるだけでなく、患者の心に寄り添うストーリーをどう伝えるかが重要です。
ここでは、実績豊富な制作会社を選ぶためのポイントと、
具体的な成功事例として株式会社ヴォイスが手がけた「クリニック」のサイトを紹介します。





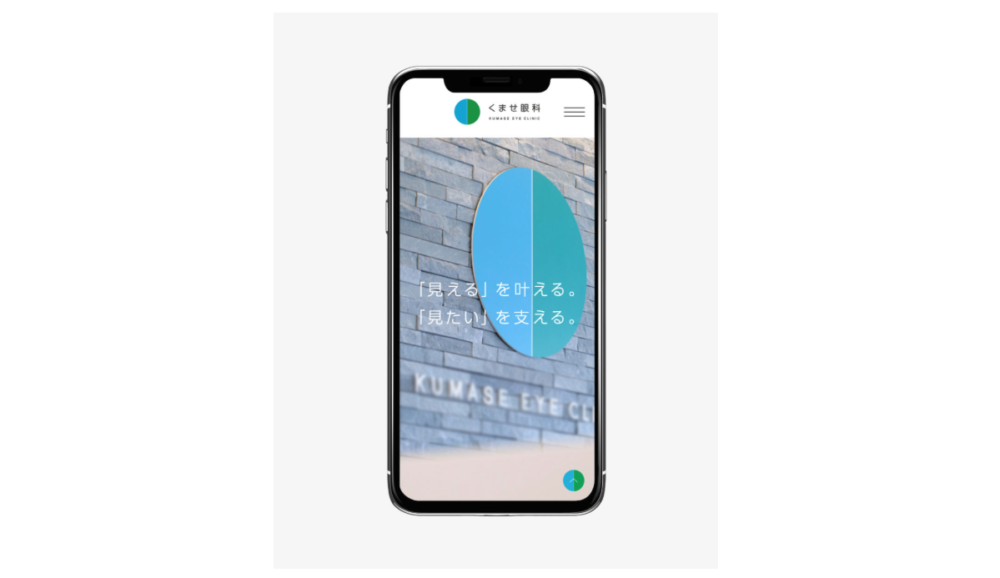
1. 具体的な制作事例を確認する
制作会社を選ぶ際は、実際にどのようなサイトを作っているかを確認するのが最も確実です。
たとえば、株式会社ヴォイスが制作したクリニックでは、産科・婦人科というデリケートな診療科目に合わせ、
「いのちの協奏曲をつむぐ」というテーマをビジュアル化。
トップページでは、医師やスタッフを“奏者”に見立てたイラストが登場し、音楽のように命を紡ぐクリニックの姿勢をやさしいトーンで表現しています。
淡いピンクと生成色を基調としたデザインは、温もりと清潔感を両立。
また、診療案内や予約ページ、アクセスマップなどがスマートフォンでも見やすい設計になっており、利用者の利便性にも配慮されています。
このように、単なる情報掲載ではなく、理念をデザインに昇華する制作姿勢が、ヴォイスの強みといえます。
2. 業界の評価や口コミを確認する
医療機関のホームページ制作には、医療広告ガイドラインへの理解や患者心理への配慮が欠かせません。
ヴォイスは、産科・婦人科、整形外科、眼科など幅広い診療科のサイトを手がけ、
「提案が的確で安心して任せられた」「開院準備から公開まで丁寧にサポートしてくれた」などの声を多数いただいています。
また、単なる制作にとどまらず、広告・SNS運用・SEO対策といった集患支援まで一貫して行える点も高く評価されています。
▶︎制作実績はこちらからご覧ください。
3. 専門性を持つスタッフがいるかを確認する
クリニックのサイトは、業界特有の表現制限や広告規制に配慮しながら制作する必要があります。
そのため、医療分野の制作経験を持つスタッフが在籍しているかどうかが重要な判断基準です。
株式会社ヴォイスでは、医療機関や病院の案件を数多く担当してきたディレクター・デザイナーがチームで対応。
開院前のブランディング提案から、開院後の運用・広告連携までをワンストップでサポートしています。
実際にクリニックのサイトでも、開院に合わせて予約導線の最適化・SNS連携・情報更新のしやすさを重視した設計がなされました。
選ぶ際のチェックポイント
クリニックのホームページ制作会社を選ぶときは、「見た目の好み」や「価格の安さ」だけで判断するのは危険です。
医療機関のWebサイトは、医療広告ガイドラインへの準拠、患者との信頼形成、そして長期的な運用が前提になります。
そのため、制作会社を選定する際には、料金・サポート・対応力という3つの観点をしっかり検討することが必要です。
1. 料金体系を明確にする
「初期費用+月額費用」や「ページ数ごとの料金」「オプション機能の追加費用」など、各社でプラン内容が異なります。
見積もりを依頼するときは、
•デザイン費用にどこまで含まれているか(写真撮影・文章作成など)
•更新や修正が有料か無料か
•契約期間や解約時の条件
といった点を具体的に質問しておきましょう。
費用の比較をする際は、“安い=最適”とは限りません。
「必要な要素を満たしたうえで、無理のない金額か」を判断軸にすることが大切です。
実際に弊社ヴォイスが制作を担当したクリニックサイト制作の場合、
コンセプト開発からデザイン・取材・写真撮影を含めたフルオーダープランでおよそ300万円ほどの制作費でした。
診療科目の特性に合わせて、やわらかな配色とスマートフォン対応を重視した構成で、
公開後は地域検索からのアクセス数が大幅に増加しています。
このように、単なる価格比較ではなく、「どこまでを任せるか」「どんな成果を期待するか」を基準に選ぶことで、
費用対効果の高いホームページ制作が実現します。
信頼されるクリニックづくりの第一歩として
クリニックのホームページは、単なる情報発信の場ではなく、「患者さんとの信頼を築くための第一歩」です。
デザインや機能の充実はもちろん、伝えたい想いや理念を丁寧に設計することで、
“地域に根ざした信頼される医療機関”としてのブランドが育っていきます。
これからの時代、オンラインでの存在感を高めることが、患者さんに選ばれるクリニックづくりの最良のスタートです。
AUTHOR:
VOICE
CONTENTS
ホームページ XLIX
「初心者でもわかるホームページ制作Q&A|
費用・集客・AI活用まで解説」
ホームページ XLVIII
「失敗事例から見えた、企業のホームページ制作会社の選び方と成功パターン」
ホームページ XLVII
中小企業ブランディング成功事例|事例で学ぶ成功の秘訣
ホームページ XLVI
成功するホームページリニューアルの考え方とは? 会社で押さえるべきポイントと進める際の視点を解説
ホームページ XLV
「会社の印象を変える!ブランディングデザインの理解と実践」
ホームページ XLIV
「大学ブランディング戦略の成功事例6選と実施ステップ」
ホームページ XLIII
「ブランディングにおけるホームページの役割とそのメリット」
ホームページ XLII
「2025年版!福井のホームページ制作会社徹底比較」
ホームページ XLI
「2025年版!SEO対策会社の選び方と特徴を解説」
ホームページ XL
「ホームページ製作費用の全体像と目的別相場をわかりやすく解説【2025年版】」
ホームページ XXXIX
「クリニックのためのホームページ制作ガイド【2025年版】」
ホームページ XXXVIII
LLMOとは
~検索から対話へ、これからのSEOの進化~
ホームページ XXXⅦ
ブランディング視点で見るWebサイトのあるべき姿
ホームページ XXXⅥ
素敵なホームページが意味を持たない理由
ホームページ XXXⅤ
「なぜ反応がない?」ホームページを公開したのにお問い合わせが来ない理由とは
ホームページ XXXⅥ
金沢でホームページ制作を考える|ホームページを「つくる前」に考えておきたい補助金の話
ホームページ XXXⅤ
Webサイト制作を経営戦略の一部として考える|成果につながるサイト設計とは?
ホームページ XXXⅣ
ブランディングを成功させるホームページ制作のポイント
ホームページ XXXⅢ
ホームページリニューアルで企業の成果を最大化する方法
ホームページ XXXⅡ
ホームページのトラフィックを増やすための基本戦略
ホームページ XXXⅠ
ホームページのデザインとブランディングの重要性
ホームページ XXX
モバイルフレンドリーなホームページ制作の重要性と実現方法
ホームページ XX Ⅸ
なぜホームページでブランディング差がつくのか?webサイト制作会社が解説
ホームページ XX Ⅷ
ターゲット市場に最適化したホームページ制作の方法
ホームページ XX Ⅶ
UXデザインでユーザーを惹きつけるホームページ制作
ホームページ XX Ⅵ
ホームページでビジネスを成長させるための戦略
ホームページ XX Ⅴ
ホームページの開設目的と役割
ホームページ XX Ⅳ
パーパスブランディングの重要性:企業のビジョンを具現化するデザイン戦略
ホームページ XX Ⅲ
モバイルファースト時代におけるホームページ制作の重要性
ホームページ XX Ⅱ
デザインと課題解決の融合:企業の本当の価値を引き出すブランディング
ホームページ XX I
デザインの力で価値を可視化する:UI/UXの未来像
ホームページ XX
問い合わせが急増!ホームページで効果的なCTA設置の秘訣
ホームページ ⅩⅨ
ブランディングとECの融合:オンラインビジネスの新たな潮流
ホームページ ⅩVIII
マーケティングから始まるホームページ制作の成功法則
#ホームページ ⅩⅦ
ホームページの集客術 SNSの効果的な活用法
#ホームページ ⅩⅥ
AIの進化と共に変わるホームページ制作:新たな関係性の創造
#ホームページ ⅩⅤ
ホームページと採用:過去の教訓と未来への展望
#ホームページ ⅩⅣ
企業の顔となるホームページ:ブランディング戦略を活かした制作術
ホームページ ⅩIII
ブランディングの核心:ゴールデンサークルを活用した価値の可視化
ホームページ ⅩⅡ
ホームページ制作におけるChatGPTの役割と新時代のSEO戦略
ホームページ ⅩⅠ
ホームページの保守管理とSEO|メンテナンスのSEOへの影響
ホームページ Ⅹ
SEOとGA4|新しいアナリティクス時代の最前線
ホームページ Ⅸ
コンテンツファーストなホームページ制作
ホームページ Ⅷ
効果的なWEBサイト制作のポイント|目的を明確にする理由
ホームページ Ⅶ
金沢でのホームページ制作費用:予算別ガイドと選び方
#ホームページ Ⅵ
SEO対策の種類と詳細:内部対策と外部対策の違いについて
#ホームページ Ⅴ
SEO対策で変わるホームページの可能性:効果的な戦略と実施法
#ホームページ Ⅳ
ユーザビリティとアクセシビリティ Webサイトの新たな標準
#ホームページ Ⅲ
Webサイトのレスポンシブデザイン モバイルフレンドリーの重要性
#ホームページ Ⅱ
ホームページ作成を依頼する前に知っておきたい5つのポイント
#ホームページ Ⅰ