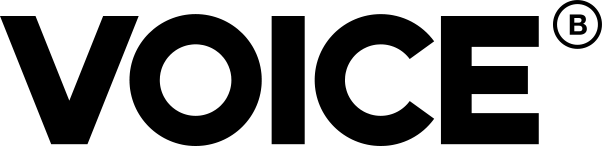ホームページ XXXVIII
LLMOとは
~検索から対話へ、これからのSEOの進化~
ここ数年、私たちの「情報の探し方」は大きく変わろうとしています。
これまでインターネットで何かを調べるとき、多くの人はGoogleなどの検索エンジンを使い、検索結果の中から答えを見つけてきました。いわゆるSEO(検索エンジン最適化)は、この検索結果の上位に表示されることを目的として発展してきたのです。
しかし今、ChatGPTやGeminiといった生成AIの登場により、ユーザーの行動は「検索してページを読む」から「AIに直接質問して答えを得る」へと大きくシフトし始めています。AIはインターネット上にある膨大な情報をまとめ、自然な言葉で即座に答えを返してくれるため、従来の検索のプロセスを短縮してしまうのです。
この変化は、企業の情報発信やマーケティングに大きな影響を与えます。なぜなら、ユーザーがAIに質問したときに、自社の情報が回答に含まれなければ「存在しないもの」として扱われてしまう可能性があるからです。SEOの時代には「検索順位」が競争の軸でしたが、これからは「AIに選ばれるかどうか」が競争の軸になるのです。
こうした新しい考え方を「LLMO(Large Language Model Optimization)」と呼びます。これは単なる流行語ではなく、今後の情報の届け方を大きく変えるキーワードです。LLMOは、AIが参照する情報として信頼されるかどうか、そして回答に反映されるかどうかを意識して情報を設計する取り組みです。
これからの時代、ホームページや記事は「検索に評価されるため」ではなく「AIに信頼され、引用されるため」に存在する――。
そんな大きな時代の転換点に、私たちは立っています。
01 LLMOとは
大規模言語モデルに最適化するという考え方
LLMO(Large Language Model Optimization)は、その名の通り「大規模言語モデル(LLM)」に対して最適化を行うという発想です。 これまでのSEOでは、Google検索やYahoo!検索などのアルゴリズムを理解し、キーワードやリンク構造を調整することで上位表示を狙ってきました。
一方、LLMOは少し視点が異なります。ChatGPTやGeminiといった生成AIは、ユーザーの質問に対してWeb上の膨大な情報を参照しながら、文章として自然な回答をつくります。そのため、従来の「検索結果に出る」ことよりも、AIが自社の情報を理解し、回答に組み込んでくれるかどうかが重要になるのです。
つまり、LLMOとは「AIにとって読みやすく、信頼できる形で情報を発信すること」。 技術的な小手先の調整ではなく、本質的に価値ある情報を整理して届ける姿勢が求められます。これこそが、SEOから一歩進んだ最適化の考え方だといえるでしょう。
ポイントはAIに理解される情報
LLMOに取り組むうえで欠かせない視点は、AIにとって理解されやすい情報であるかどうかです。 人間の読者であれば、多少曖昧な表現でも「なんとなく伝わる」ことがありますが、生成AIは文章を構造的に分析し、文脈や根拠をもとに回答をつくります。そのため、情報が整理されていなかったり、裏付けが弱かったりすると、AIにとっては「信頼しにくい情報」と判断され、回答には使われなくなる可能性が高いのです。
ここで求められるのは、次のような工夫です。
——————————————————————————–
•明確な構造
見出しや段落で情報を整理し、「問い」と「答え」が分かりやすい文章にする。
•一次情報や具体例
実績データや体験談など、オリジナルの情報を含めることで「信頼できる情報源」と認識されやすくなる。
•専門性と一貫性
同じテーマについて継続的に情報を発信することで、「この分野ならこの企業が詳しい」とAIに学習されやすくなる。
——————————————————————————–
つまり、LLMOで大切なのは「AIに読み解かれやすい文章設計」と「信頼される情報の蓄積」です。 これは決して難しいテクニックではなく、読み手に誠実に情報を届ける姿勢を徹底することが、そのままAIにも伝わるのです。
信頼される情報が選ばれる
生成AIは膨大な情報を参照しながら回答を作りますが、そのすべてを均等に扱うわけではありません。回答の中に取り入れられるのは、AIが「信頼できる」と判断した情報です。 では、AIが信頼を置くのはどのような情報でしょうか。
——————————————————————————–
•裏付けのある一次情報
他のサイトの受け売りではなく、自社で取得したデータ、事例、調査結果といった一次情報は高く評価されやすい。
•専門家や組織による発信
個人の意見よりも、専門家や企業といった“責任の所在が明確”な情報源が重視される。
•更新され続けている情報
古い情報よりも、定期的に更新されている最新の情報が優先される。
——————————————————————————–
つまり、LLMOの本質は「AIに信頼される情報発信者になること」です。 単に記事数を増やすのではなく、「この会社が言うなら信頼できる」と思わせる根拠や一貫性を積み重ねることが、生成AIに選ばれる条件となります。
この姿勢は、人間の読者にとっても同じこと。信頼性を大切にした発信は、結果的にユーザーからの共感や行動にもつながっていきます。
SEOとの違いは「競争の舞台」
従来のSEOでは、GoogleやYahoo!などの検索結果ページで「いかに上位に表示されるか」が最大の目的でした。ユーザーは検索結果の一覧から気になるサイトをクリックし、そこから情報を得るという行動パターンが中心だったからです。
しかしLLMOでは、この競争の舞台そのものが変わります。ユーザーがAIに質問したとき、検索結果の一覧を見ることなく、その場で回答を得るケースが増えているからです。つまり、クリックされる前に「AIの回答の中に含まれるかどうか」で存在が決まってしまうのです。
この変化は、企業にとって大きな意味を持ちます。SEOでは「順位」が可視化されましたが、LLMOでは「AIがどの情報を引用するか」が重要であり、その判断基準はより“信頼性”や“価値の高さ”に寄っています。
言い換えると、SEOの競争が「検索結果ページ」という目に見える舞台で行われていたのに対し、LLMOの競争は「AIが回答をつくる過程」という見えない舞台で行われているのです。 その舞台で選ばれるためには、単なるテクニックではなく、真に価値ある情報をどう提供するかが問われる時代になったといえるでしょう。
02 なぜLLMOが必要なのか
検索行動の変化
これまで私たちは「検索 → リンクをクリック → 情報を読む」という流れで情報を得てきました。 しかし、生成AIの登場によって、ユーザーは「質問 → その場で回答を得る」という行動を取るようになっています。 つまり、「検索結果一覧を比較する」というステップを飛ばしてしまうのです。
AIに取り上げられなければ“存在しない”に等しい
もしAIの回答に自社の情報が含まれなければ、ユーザーはその企業の存在に気づくことさえできません。
これはSEOの時代以上にシビアな状況であり、AIに引用されるかどうかが、そのまま認知の有無を決定づけるのです。
問い合わせや購買行動の入口が変わる
これからは「AIにどう紹介されたか」が、ユーザーの信頼や行動に直結します。 AIが提示する選択肢に入っていなければ、検討テーブルにすら乗れない。逆に、AIに取り上げられた情報は一気に信頼度を高め、問い合わせや購買のきっかけになっていきます。
早期に取り組む企業が有利になる
LLMOはまだ新しい考え方ですが、だからこそ早く取り組んだ企業ほど大きなアドバンテージを得られます。 AIは「これまでの情報」を学習する仕組みを持つため、今から積み重ねる情報発信は将来のAI回答に反映されやすくなるのです。
03 LLMOの具体的なアプローチ
一次情報を発信する
生成AIは、他のサイトから引用しただけの情報よりも「一次情報」を優先します。 例えば、自社で実施した調査データや成功事例、現場で得られた知見などは、AIにとって信頼性の高い材料となります。 他にはない“オリジナルの強み”を積極的に発信することが、AIに選ばれる近道です。
構造化された文章にする
AIは情報を読み解く際、文章の構造を重要視します。 見出しや箇条書きを使って論理の流れを整理することで、「この部分は質問の答えだ」とAIに理解されやすくなります。 Q&A形式やハウツー記事のように、明確な問いと答えを意識するのも効果的です。
専門性と継続性を示す
AIは「この分野ならこの企業」と認識できるかどうかを見ています。 断片的に情報を出すのではなく、同じテーマについて継続的に発信することで専門性が伝わりやすくなります。 企業ブログやコラムを継続的に更新することは、まさにLLMO対策の基本行動です。
信頼を裏付ける情報を整える
企業のプロフィール、実績紹介、外部からの評価(メディア掲載・レビューなど)は、AIにとって「この情報源は信頼できる」と判断する材料になります。 発信する情報そのものだけでなく、それを支える背景情報を整備しておくことが重要です。
04 LLMO時代に求められる本質
テクニックではなく姿勢が問われる
従来のSEOは「キーワード選定」「リンク構造」といったテクニカルな要素が大きな役割を持っていました。 しかしLLMOは、AIを“だます”ような小手先の手法は通用しません。 必要なのは 価値ある情報を正しく言語化し、誠実に発信する姿勢 です。
人間に伝わることはAIにも伝わる
AIは人間の思考や言語を学習しています。つまり「人が理解しやすい、信頼しやすい」と感じる情報は、AIにとっても扱いやすい情報です。 結局のところ、ユーザーにとって有益な情報を届けることが、最も効果的なLLMO対策となります。
ブランドの一貫性が未来を左右する
単発の記事や断片的な情報では、AIに「この企業の強みは何か」が伝わりません。 発信する言葉やコンテンツに一貫性を持たせることで、AIの学習に「ブランドの軸」が刻まれます。 これは、価格競争に巻き込まれず、自社らしい価値で選ばれるための土台にもなります。
未来の“存在証明”としてのLLMO
AIが回答の中心となる時代において、「AIに取り上げられるかどうか」は企業にとって存在証明に近い意味を持ちます。 見つけてもらうためではなく、未来の市場に存在し続けるための戦略として、LLMOは欠かせない取り組みになっていくでしょう。
AUTHOR:
VOICE
CONTENTS
ホームページ XLV
成功するホームページリニューアルの考え方とは? 会社で押さえるべきポイントと進める際の視点を解説
ホームページ XLV
「会社の印象を変える!ブランディングデザインの理解と実践」
ホームページ XLIV
「大学ブランディング戦略の成功事例5選と実施ステップ」
ホームページ XLIII
「ブランディングにおけるホームページの役割とそのメリット」
ホームページ XLII
「2025年版!福井のホームページ制作会社徹底比較」
ホームページ XLI
「2025年版!SEO対策会社の選び方と特徴を解説」
ホームページ XL
「ホームページ製作費用の全体像と目的別相場をわかりやすく解説【2025年版】」
ホームページ XXXIX
「クリニックのためのホームページ制作ガイド【2025年版】」
ホームページ XXXVIII
LLMOとは
~検索から対話へ、これからのSEOの進化~
ホームページ XXXⅦ
ブランディング視点で見るWebサイトのあるべき姿
ホームページ XXXⅥ
素敵なホームページが意味を持たない理由
ホームページ XXXⅤ
「なぜ反応がない?」ホームページを公開したのにお問い合わせが来ない理由とは
ホームページ XXXⅥ
金沢でホームページ制作を考える|ホームページを「つくる前」に考えておきたい補助金の話
ホームページ XXXⅤ
Webサイト制作を経営戦略の一部として考える|成果につながるサイト設計とは?
ホームページ XXXⅣ
ブランディングを成功させるホームページ制作のポイント
ホームページ XXXⅢ
ホームページリニューアルで企業の成果を最大化する方法
ホームページ XXXⅡ
ホームページのトラフィックを増やすための基本戦略
ホームページ XXXⅠ
ホームページのデザインとブランディングの重要性
ホームページ XXX
モバイルフレンドリーなホームページ制作の重要性と実現方法
ホームページ XX Ⅸ
なぜホームページでブランディング差がつくのか?webサイト制作会社が解説
ホームページ XX Ⅷ
ターゲット市場に最適化したホームページ制作の方法
ホームページ XX Ⅶ
UXデザインでユーザーを惹きつけるホームページ制作
ホームページ XX Ⅵ
ホームページでビジネスを成長させるための戦略
ホームページ XX Ⅴ
ホームページの開設目的と役割
ホームページ XX Ⅳ
パーパスブランディングの重要性:企業のビジョンを具現化するデザイン戦略
ホームページ XX Ⅲ
モバイルファースト時代におけるホームページ制作の重要性
ホームページ XX Ⅱ
デザインと課題解決の融合:企業の本当の価値を引き出すブランディング
ホームページ XX I
デザインの力で価値を可視化する:UI/UXの未来像
ホームページ XX
問い合わせが急増!ホームページで効果的なCTA設置の秘訣
ホームページ ⅩⅨ
ブランディングとECの融合:オンラインビジネスの新たな潮流
ホームページ ⅩVIII
マーケティングから始まるホームページ制作の成功法則
#ホームページ ⅩⅦ
ホームページの集客術 SNSの効果的な活用法
#ホームページ ⅩⅥ
AIの進化と共に変わるホームページ制作:新たな関係性の創造
#ホームページ ⅩⅤ
ホームページと採用:過去の教訓と未来への展望
#ホームページ ⅩⅣ
企業の顔となるホームページ:ブランディング戦略を活かした制作術
ホームページ ⅩIII
ブランディングの核心:ゴールデンサークルを活用した価値の可視化
ホームページ ⅩⅡ
ホームページ制作におけるChatGPTの役割と新時代のSEO戦略
ホームページ ⅩⅠ
ホームページの保守管理とSEO|メンテナンスのSEOへの影響
ホームページ Ⅹ
SEOとGA4|新しいアナリティクス時代の最前線
ホームページ Ⅸ
コンテンツファーストなホームページ制作
ホームページ Ⅷ
効果的なWEBサイト制作のポイント|目的を明確にする理由
ホームページ Ⅶ
金沢でのホームページ制作費用:予算別ガイドと選び方
#ホームページ Ⅵ
SEO対策の種類と詳細:内部対策と外部対策の違いについて
#ホームページ Ⅴ
SEO対策で変わるホームページの可能性:効果的な戦略と実施法
#ホームページ Ⅳ
ユーザビリティとアクセシビリティ Webサイトの新たな標準
#ホームページ Ⅲ
Webサイトのレスポンシブデザイン モバイルフレンドリーの重要性
#ホームページ Ⅱ
ホームページ作成を依頼する前に知っておきたい5つのポイント
#ホームページ Ⅰ