ホームページ XXXⅤ
Webサイト制作を経営戦略の一部として考える|成果につながるサイト設計とは?
なぜ今「Webサイト」が経営に直結するのか
近年、Webサイトは単なる会社案内や商品紹介の場にとどまらず、企業の経営成果に直結する重要な戦略ツールへと変化しています。かつては名刺代わりにとりあえず作られることも多かったWebサイトですが、今では売上の獲得、顧客との関係構築、採用強化、ブランディングなど、あらゆる経営課題を解決する手段として活用されています。
特に中小企業や地方企業においても、「営業に行かずに受注が取れるようになった」「求人広告よりも自社サイト経由で優秀な人材が集まるようになった」といった事例が数多く見られるようになりました。これは、Webサイトが“経営の前線”で機能する時代に突入したことを意味しています。
情報発信ツールから「経営戦略の中核」へと変化した背景
Webサイトの価値が高まった背景には、いくつかの社会的・技術的な変化があります。
1つは、ユーザーの情報収集行動の変化です。今やほとんどの顧客が、商品・サービスの比較検討をWeb上で行っています。BtoCだけでなく、BtoBでも「まずWeb検索で企業を知る」という流れが当たり前になっており、“第一印象はWebで決まる”と言っても過言ではありません。
もう1つは、デジタル技術とマーケティングの進化です。SEOやコンテンツマーケティング、MA(マーケティングオートメーション)などの活用により、Webサイトが“待ちの営業”ではなく“攻めの営業ツール”へと変化しました。広告費に頼らず、安定的に見込み客を獲得できる仕組みとして機能するようになったのです。
また、2020年以降のコロナ禍によって、対面営業やリアルイベントが制限されたことで、Webにおける顧客接点の重要性が一気に高まりました。この流れは収束後も定着し、今や企業のWebサイトは、リアルと並ぶ「もう一つの経営拠点」となっています。
このように、Webサイトは単なる広報手段ではなく、経営の方向性と密接に結びついた戦略的なツールとして再定義されつつあります。本記事では、Webサイトを経営戦略の一部として捉える重要性と、具体的な活用ステップについて詳しく解説していきます。
01 経営戦略とWebサイトの関係性
経営課題を解決する「Webサイト」の役割
企業が直面する経営課題は多岐にわたります。たとえば、「新規顧客が増えない」「優秀な人材が集まらない」「ブランド認知が広がらない」といった悩みは、多くの経営者に共通するものです。こうした課題に対して、Webサイトは“経営の打ち手”として活用できるポテンシャルを持っています。
Webサイトは24時間365日稼働し、情報発信・営業・採用・ブランド強化といった機能を果たします。これは、人的リソースが限られた企業にとっては非常に大きな価値です。たとえば、営業担当者が直接アプローチできる人数には限界がありますが、Webサイト経由なら数十倍・数百倍の見込み客に接触可能です。
さらに近年は、顧客の検討行動がWeb上で完結する傾向が強まっています。BtoBでもBtoCでも、「問い合わせをする前」にユーザーはWeb上で企業やサービスを徹底的に比較・調査しています。この段階でWebサイトに十分な情報や信頼性がなければ、検討対象から即座に外れてしまうのです。
つまり、Webサイトは単なる「情報提供の場」ではなく、ユーザーが“選ぶ・選ばない”を判断する最前線の営業・採用ツールとなっています。
売上・採用・認知拡大に直結する設計の考え方
経営戦略と連動したWebサイトを作るためには、サイト自体の設計思想が重要です。ただ見やすく、きれいに作るだけでは経営へのインパクトは限定的です。経営目標を起点とした設計が不可欠なのです。
たとえば「売上向上」が目的であれば、以下のような考え方が必要です。
- ・顧客の課題を起点にしたコンテンツを配置し、SEOで流入を増やす
- ・商品・サービスの魅力を定量・定性の両面で伝え、信頼感を構築する
- ・CTA(お問い合わせや資料請求など)までの導線をスムーズに設計する
一方、「採用強化」が目的であれば、求職者に向けた情報設計や導線が重要になります。
- ・社員インタビューや社風紹介など、職場のリアルが伝わるコンテンツ
- ・応募前に不安や疑問を解消できるFAQページ
- ・採用情報への導線を明確に配置し、スマートフォンにも最適化する
また、「認知拡大」を狙う場合は、SNSや広告と連携したコンテンツ設計や、ブランドストーリーを語るページ設計が鍵を握ります。
このように、Webサイトは目的に応じて構造・内容・導線を設計することで、経営成果に直結する仕組みをつくることが可能です。
02 ありがちなWebサイト制作の失敗パターン
「とりあえず作る」では成果が出ない理由
Webサイト制作の現場では、「とりあえず会社案内としてサイトを持っておきたい」「周りが持っているから自社も必要だろう」という理由で制作が始まるケースが少なくありません。しかし、この“とりあえず”という姿勢こそが、成果につながらない最大の原因です。
成果を出しているWebサイトには、共通して「目的」と「戦略」が存在します。どんなユーザーに何を届け、どんなアクションを起こしてもらいたいのか。どのように流入を増やし、どこで信頼を獲得し、どこでコンバージョンにつなげるのか。こうした設計がなされていなければ、Webサイトは単なる“飾り”になってしまいます。
特に、経営層が「サイトは広報担当に任せておけばいい」と考えてしまうと、戦略的な視点が抜け落ちたままプロジェクトが進行してしまいます。結果、公開後もアクセスが伸びず、問い合わせも増えず、「結局、Webは効果がない」という誤解につながることもあります。
Webサイトは「作って終わり」ではなく、「使って成果を出す」ことが本質です。経営目標とつながっていないWebサイトは、どれだけ見た目が整っていても投資対効果が低くなるのです。
見た目重視・費用重視が招く落とし穴
もう一つのよくある失敗パターンが、「見た目重視」「費用重視」で制作会社を選んでしまうケースです。
デザインが美しいサイトや、価格が安い制作プランには確かに魅力があります。しかし、見た目が良くてもコンテンツの設計や導線が不十分であれば、ユーザーはすぐに離脱してしまいます。また、低コストにこだわるあまり、必要な設計やマーケティングの観点が抜け落ちたWebサイトになることも珍しくありません。
とくに注意すべきなのは、「テンプレートで簡単に作れます」「納期がとても短いです」といった売り文句。こうしたサービスは一見手軽に見えますが、自社の経営戦略や顧客の行動特性に即した設計がされていないことが多く、長期的に成果が出にくい傾向があります。
また、見た目ばかりを気にして写真やアニメーションに力を入れすぎると、ページの読み込み速度が遅くなり、SEOやユーザー体験に悪影響を及ぼすこともあります。華やかで美しいだけのサイトは、ビジネス上の成果につながらなければ本末転倒です。
Webサイトは企業の「営業担当」「採用担当」「広報担当」として働く存在です。見た目や初期費用よりも、「どのような役割を果たすのか」「どのように成果につなげるのか」といった設計と運用体制にこそ、コストをかけるべきなのです。
03 経営戦略と連動したWebサイトを作るステップ
Webサイトを経営戦略と連動させ、成果を出すためには、感覚的な制作ではなくロジカルなステップに基づいた設計プロセスが不可欠です。以下では、成果を上げるWebサイト構築の6つのステップをご紹介します。
1.経営目標の明確化とWebの位置づけ
最初に行うべきは、「Webサイトを通じて何を達成したいのか」という経営目標の明確化です。新規顧客の獲得、既存顧客との関係強化、採用強化、ブランディング──目的によってWebサイトの構造・内容・KPIはまったく異なります。
同時に、「Webは営業の代替か補完か?」「採用の一次接点か、最終判断の補助か?」といったWebサイトの位置づけを、事業全体のなかで整理する必要があります。これが曖昧なまま制作を始めてしまうと、表面的な情報の羅列に終わってしまい、成果にはつながりません。
2.ペルソナとカスタマージャーニーの設計
次に重要なのが、ターゲットユーザー像(ペルソナ)の具体化と、そのユーザーがどのような情報を求め、どんなプロセスで意思決定するかを可視化したカスタマージャーニーの設計です。
ユーザーは何に悩み、何を調べ、どんなタイミングで問い合わせや応募をするのか──この流れを踏まえた設計を行うことで、コンテンツの内容や配置、導線の設計が的確になります。
「誰に向けて発信するか」が明確でないWebサイトは、結果として誰の心にも響かないものになります。
3.競合・市場調査を踏まえた差別化戦略
自社の強みを正しく伝えるためには、競合他社や市場の調査が欠かせません。ユーザーが他にどのような選択肢を持っているのか、競合はどのような訴求をしているのかを把握したうえで、自社だけの価値(独自性)を明確にしましょう。
たとえば競合が価格を前面に押し出している場合、自社は品質やサポート体制を強みに訴求するなど、ポジショニングの違いを明示することが重要です。差別化されたメッセージは、ユーザーの記憶に残りやすく、選ばれる確率を高めます。
4.コンテンツ計画とSEO戦略の策定
Webサイトの価値を最大化するには、検索エンジンからの集客が欠かせません。そこで重要になるのがコンテンツマーケティングとSEO戦略です。
ペルソナが検索しそうなキーワードを洗い出し、それに応える形で有益なコンテンツ(記事、コラム、事例紹介など)を計画的に制作・発信していきます。これにより、単なる名刺代わりではなく「見込み客を呼び込む集客装置」として機能するWebサイトになります。
同時に、検索順位を左右するタイトル、見出し構造、内部リンク、メタ情報の最適化など、技術的なSEOも計画段階で考慮しましょう。
5.デザイン・UI/UXの最適化
デザインやUI/UX(ユーザー体験)も、単に「見た目の美しさ」を追求するのではなく、ユーザーが目的の情報にストレスなくたどり着けるかどうかを基準に最適化する必要があります。
特に重要なのは次の3点です。
- ・視線の動きを意識したレイアウト(情報の優先度を視覚的に示す)
- ・スマホでも快適に閲覧・操作できるレスポンシブ設計
- ・行動(問い合わせ・購入・応募)につながる導線とボタン配置
ユーザーは「使いづらい」と感じた瞬間に離脱してしまいます。ユーザー目線での操作性とナビゲーション設計が、成果を左右する重要な要素です。
6.運用と改善の体制づくり
公開して終わり、ではWebサイトは成果を出し続けられません。重要なのは継続的に改善していく運用体制の構築です。
Googleアナリティクスやヒートマップなどのツールを使ってアクセスデータを分析し、どのページが読まれているか、どこで離脱しているかを把握します。その結果をもとに、コンテンツの見直しや導線の改善を繰り返すことで、Webサイトの成果は着実に向上していきます。
また、運用には担当者のリソースやノウハウも必要になるため、社内体制の整備や制作会社との連携方法も事前に決めておくことが理想的です。
04 成功事例から学ぶ、経営戦略型Webサイト
BtoB企業:営業プロセスの効率化と商談創出
BtoB企業においては、Webサイトが「営業の入り口」として確立されてきています。
従来は展示会・紹介・テレアポなどが中心だった新規開拓において、近年では「製品紹介ページ+技術コラム+導入事例」を組み合わせたWeb戦略を通じて、月数十件以上の問い合わせを獲得している企業も少なくありません。
特に、産業機器・ITサービス・部品加工などの分野では、以下のような変化が進んでいます。
- ・「検索で技術課題のヒントを探すエンジニア」向けに専門コラムを発信
- ・「〇〇業界 導入事例」での流入を狙ってケース紹介ページを強化
- ・ダウンロード資料やホワイトペーパーを設置し、リード情報を獲得
こうした動線設計により、営業担当が最初に会う前に顧客が“温まった状態”になっているため、商談化率も向上する傾向があります。
採用難業界:Webによる母集団形成と共感獲得
医療・福祉・建設・ITなど、人材確保が難しい業界では、採用サイトの充実が成果に直結する例が急増しています。
とくに若年層(20代〜30代)は、応募前に企業のWebサイトやSNSを細かくチェックする傾向が強く、下記のような施策が多くの企業で実践されています。
- ・社員インタビューや「1日の仕事の流れ」など、現場のリアルを伝えるページの設置
- ・自社のカルチャー・理念・キャリアパスを明文化した「採用ブランディング」
- ・スマホ最適化とエントリーフォームの簡素化で、応募ハードルを下げる
実際、求人媒体経由よりも「採用サイト経由の応募者の定着率が高い」と答える企業も多く、Webを介した採用広報の重要性が明らかになっています。
地域ビジネス:検索とSNSの両軸で認知と集客を強化
飲食店、美容室、整骨院、小売業などの地域密着型ビジネスでも、Webサイトは経営に欠かせないツールになっています。
特にスマホでの「近くのお店検索」や「○○市 ランチ」などのローカルSEOへの対応は、新規来店の大きな起点になっています。以下のような施策が効果的とされています。
- ・Googleビジネスプロフィールと連動した店舗情報ページの最適化
- ・「メニュー紹介」「スタッフ紹介」など、親しみや信頼を与えるコンテンツの整備
- ・SNSとの連携によるリアルタイムの情報発信
実際に、SEO対策を行った地域店舗のWebサイトでは、来店予約やテイクアウト注文が増加したという報告も多く、エリアビジネスでもWeb活用は売上拡大に直結しています。
これらの事例から読み取れることは、「自社にとってのWebの役割」を明確に定義し、戦略に基づいた設計を行えば、業種を問わず成果が出るということです。
- ・BtoBでは「信頼獲得と商談創出」
- ・採用難業界では「共感形成と応募の導線設計」
- ・地域ビジネスでは「認知拡大と来店促進」
Webサイトは経営課題に対する“実践的な解決手段”であるという認識を持つことが、成功への第一歩です。
05 経営者・担当者が押さえておきたいポイント
Webサイトを経営戦略の一部として位置づけるためには、経営者自身の関与や、プロジェクトの進め方に対する姿勢も大きく影響します。ここでは、経営者・担当者として意識しておきたい2つのポイントをご紹介します。
制作会社に「戦略的思考」を求めるべき理由
Webサイト制作を外部に依頼する際、多くの企業が「デザイン力」や「価格」だけでパートナーを選びがちです。しかし、成果を生むWebサイトをつくるうえで本当に重要なのは、“戦略的思考”を持った制作パートナーかどうかです。
Webサイトは、単なるビジュアル制作ではありません。
企業の「何を」「誰に」「どう届けるか」という経営上の意思決定を具現化するツールです。つまり、以下のような視点で提案ができる制作会社こそが、成果につながるパートナーといえます。
- ・目的やKPIから逆算したサイト構造の設計ができる
- ・ターゲットユーザーの行動心理を踏まえたコンテンツ戦略を提案できる
- ・SEOや広告、SNSなど周辺施策との連動を考慮している
- ・公開後の運用フェーズまで含めた体制やアドバイスを持っている
このような観点で制作会社を選定し、「自社の経営課題を一緒に考えてくれるかどうか」を判断基準に加えることで、見た目だけのWebサイトではなく“成果に直結するWebサイト”を作ることが可能になります。
単なる発注者ではなく、パートナーとしての関係構築
成果を上げるWebサイト制作には、発注側の姿勢も重要なカギを握ります。とくに中小企業やスタートアップでは、経営者自身がプロジェクトの中心に立ち、意思決定をスピーディに行うことで、Webの力を最大限活用できるようになります。
「業者に丸投げすればなんとかしてくれる」というスタンスでは、自社の強みやビジョンを正確に反映したWebサイトにはなりません。逆に、制作側としっかりと対話し、自社の状況や課題、戦略の方向性を共有すれば、より精度の高い提案や改善策が返ってくるようになります。
また、制作が完了した後も、公開→運用→改善というサイクルを一緒に回していく関係性が理想です。サイト公開はゴールではなくスタートです。PDCAを回し、ユーザーの行動や検索トレンドの変化に合わせて継続的に進化できるパートナーシップを築くことで、Webサイトは“経営の資産”として成長していきます。
経営者・担当者の役割は、単にサイト制作を「管理すること」ではなく、“戦略を共に育てること”です。制作会社を「外注先」ではなく、「共創するパートナー」と捉えることで、Webサイトの本来の力を最大限に引き出すことができます。
06 まとめ|Webサイトは“資産”であり“戦略ツール”
長期視点での設計が成果を生む
Webサイトは、単なる“デジタル上のパンフレット”ではなく、企業が成長していくための戦略的な資産です。短期的な見栄えや初期コストだけにとらわれず、「3年後、5年後にも機能し続けるサイト」をどう設計するかが、Web活用の成否を分けます。
コンテンツの積み重ねはSEO資産となり、ユーザーの行動データはマーケティング改善の材料となり、社内でのナレッジは運用体制の強化につながります。
このように、Webサイトは「育てるほど価値が増していく資産」であり、時間をかけて育成する対象です。
短期的なリニューアルやリスティング広告だけに頼るのではなく、継続的な改善と価値の蓄積こそが、他社との差を広げる鍵となります。
「経営の手段」としてのWeb活用を今こそ見直す
変化の激しい市場環境や人材不足、営業活動のオンライン化など、企業を取り巻く状況はこれまで以上に複雑化しています。そのなかで、Webサイトは「経営の手段」としての役割をますます強めています。
- ・売上を増やすために、どのように見込み顧客をWebで呼び込むか
- ・採用を成功させるために、どんな企業イメージを伝えるべきか
- ・ブランドを確立するために、どのようなメッセージを発信すべきか
これらすべてに対し、Webサイトは最前線の実行手段として機能します。
今こそ、自社のWebサイトを単なるIT施策や外注物として捉えるのではなく、経営目標を達成するための武器として活用する視点が必要です。そして、そのためには、経営者自身がWebの可能性を理解し、主導していく姿勢が求められます。
Webサイトは“経営の分身”であり、“経営の未来を支えるツール”です。
「Webをどう活用するか」は、これからの時代において、企業の競争力そのものに直結します。
本記事をきっかけに、Webを経営の戦略に組み込む第一歩を踏み出していただければ幸いです。
弊社では、ブランディングでクライアントの〝潜在能力〟を引き出すクリエイティブをご提案しています。
よろしければこちらもご覧ください。
AUTHOR:
VOICE
CONTENTS
ホームページ XLV
「会社の印象を変える!ブランディングデザインの理解と実践」
ホームページ XLIV
「大学ブランディング戦略の成功事例5選と実施ステップ」
ホームページ XLIII
「ブランディングにおけるホームページの役割とそのメリット」
ホームページ XLII
「2025年版!福井のホームページ制作会社徹底比較」
ホームページ XLI
「2025年版!SEO対策会社の選び方と特徴を解説」
ホームページ XL
「ホームページ製作費用の全体像と目的別相場をわかりやすく解説【2025年版】」
ホームページ XXXIX
「クリニックのためのホームページ制作ガイド【2025年版】」
ホームページ XXXVIII
LLMOとは
~検索から対話へ、これからのSEOの進化~
ホームページ XXXⅦ
ブランディング視点で見るWebサイトのあるべき姿
ホームページ XXXⅥ
素敵なホームページが意味を持たない理由
ホームページ XXXⅤ
「なぜ反応がない?」ホームページを公開したのにお問い合わせが来ない理由とは
ホームページ XXXⅥ
金沢でホームページ制作を考える|ホームページを「つくる前」に考えておきたい補助金の話
ホームページ XXXⅤ
Webサイト制作を経営戦略の一部として考える|成果につながるサイト設計とは?
ホームページ XXXⅣ
ブランディングを成功させるホームページ制作のポイント
ホームページ XXXⅢ
ホームページリニューアルで企業の成果を最大化する方法
ホームページ XXXⅡ
ホームページのトラフィックを増やすための基本戦略
ホームページ XXXⅠ
ホームページのデザインとブランディングの重要性
ホームページ XXX
モバイルフレンドリーなホームページ制作の重要性と実現方法
ホームページ XX Ⅸ
なぜホームページでブランディング差がつくのか?webサイト制作会社が解説
ホームページ XX Ⅷ
ターゲット市場に最適化したホームページ制作の方法
ホームページ XX Ⅶ
UXデザインでユーザーを惹きつけるホームページ制作
ホームページ XX Ⅵ
ホームページでビジネスを成長させるための戦略
ホームページ XX Ⅴ
ホームページの開設目的と役割
ホームページ XX Ⅳ
パーパスブランディングの重要性:企業のビジョンを具現化するデザイン戦略
ホームページ XX Ⅲ
モバイルファースト時代におけるホームページ制作の重要性
ホームページ XX Ⅱ
デザインと課題解決の融合:企業の本当の価値を引き出すブランディング
ホームページ XX I
デザインの力で価値を可視化する:UI/UXの未来像
ホームページ XX
問い合わせが急増!ホームページで効果的なCTA設置の秘訣
ホームページ ⅩⅨ
ブランディングとECの融合:オンラインビジネスの新たな潮流
ホームページ ⅩVIII
マーケティングから始まるホームページ制作の成功法則
#ホームページ ⅩⅦ
ホームページの集客術 SNSの効果的な活用法
#ホームページ ⅩⅥ
AIの進化と共に変わるホームページ制作:新たな関係性の創造
#ホームページ ⅩⅤ
ホームページと採用:過去の教訓と未来への展望
#ホームページ ⅩⅣ
企業の顔となるホームページ:ブランディング戦略を活かした制作術
ホームページ ⅩIII
ブランディングの核心:ゴールデンサークルを活用した価値の可視化
ホームページ ⅩⅡ
ホームページ制作におけるChatGPTの役割と新時代のSEO戦略
ホームページ ⅩⅠ
ホームページの保守管理とSEO|メンテナンスのSEOへの影響
ホームページ Ⅹ
SEOとGA4|新しいアナリティクス時代の最前線
ホームページ Ⅸ
コンテンツファーストなホームページ制作
ホームページ Ⅷ
効果的なWEBサイト制作のポイント|目的を明確にする理由
ホームページ Ⅶ
金沢でのホームページ制作費用:予算別ガイドと選び方
#ホームページ Ⅵ
SEO対策の種類と詳細:内部対策と外部対策の違いについて
#ホームページ Ⅴ
SEO対策で変わるホームページの可能性:効果的な戦略と実施法
#ホームページ Ⅳ
ユーザビリティとアクセシビリティ Webサイトの新たな標準
#ホームページ Ⅲ
Webサイトのレスポンシブデザイン モバイルフレンドリーの重要性
#ホームページ Ⅱ
ホームページ作成を依頼する前に知っておきたい5つのポイント
#ホームページ Ⅰ
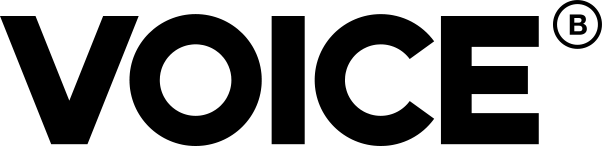

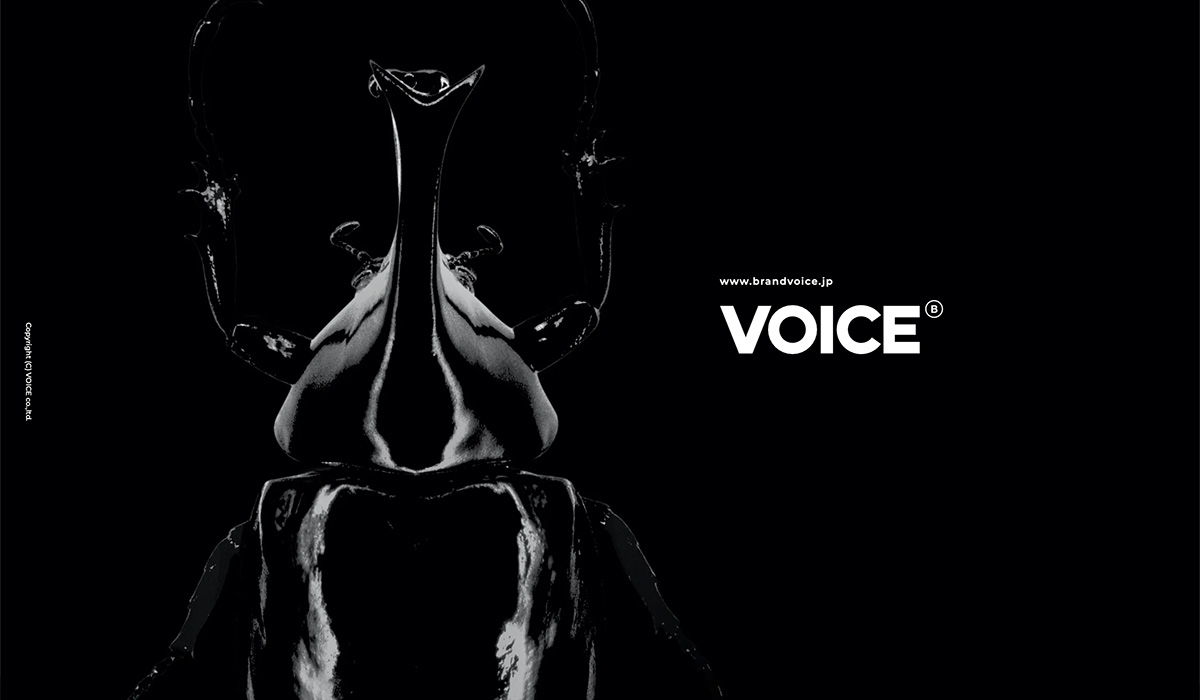 ヴォイス ホームページ
ヴォイス ホームページ