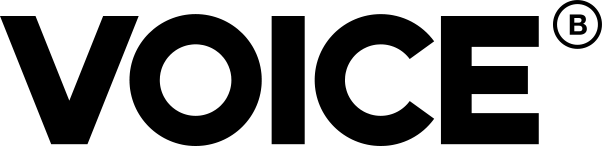ホームページ XXXⅦ
ブランディング視点で見るWebサイトのあるべき姿
01 なぜ今、ブランディング視点のWebサイトが重要なのか?
検討段階のユーザーは「デザイン」だけで判断していない
多くの企業がWebサイトを持つ現代では、デザインの良し悪しだけで差別化を図るのは難しくなっています。ユーザーは、単に“かっこいい”や“洗練されている”という見た目の印象だけでなく、その企業やサービスが自分にとって信頼できる存在かどうかを見極めようとしています。
特に検討段階のユーザーは、複数のサービスや会社を比較しながら選択肢を絞っていくため、情報の質やブランドの姿勢にまで目を向けているのです。いくらビジュアルが優れていても、コンテンツに深みがなかったり、伝えるべき価値がぼやけていたりすると、選ばれる理由になりません。
こうした状況においては、「見せ方」以上に「伝え方」や「あり方」が問われるようになっています。ブランディング視点を取り入れることで、デザインだけでは伝わりきらない企業の本質や価値観をWebサイト上に反映させ、ユーザーの信頼を得ることが可能になります。
情報があふれる時代に「共感」されるサイトが強い理由
インターネット上には無数の情報があふれており、ユーザーは1日に何十、何百というWebサイトや広告に触れています。その中で印象に残るのは、機能的な違いではなく「感情的に共感できたかどうか」という体験です。
「自分に合っている」「価値観が近い」「信頼できそう」と感じてもらうためには、企業としての“らしさ”を伝えること=ブランディングが必要です。これはロゴや色使いなどのビジュアル面だけでなく、メッセージ、トーン、構成、ストーリーなどあらゆる要素が一貫性を持って表現されているかどうかにかかっています。
共感を生むサイトは、単なる情報提供ではなく、ユーザーとの関係性を構築する入り口になります。人は感情で動き、理屈で納得します。だからこそ、感情に働きかけるブランディング設計は、今後ますますWebサイト制作において欠かせない要素になるのです。
02 ブランディングが弱いWebサイトにありがちな特徴
トンマナがバラバラ、伝えたいことが曖昧
ブランディングがうまくできていないWebサイトの典型的な特徴のひとつが、トンマナ(トーン&マナー)に一貫性がないことです。
ページごとに雰囲気が異なったり、フォントや配色、写真の雰囲気がちぐはぐだったりすると、ブランドとしての統一感が失われ、ユーザーに不安や違和感を与えます。
また、メッセージの内容が抽象的すぎたり、企業として何を伝えたいのかが曖昧だったりすると、「で、結局何が強みなの?」と感じられてしまいます。
せっかくホームページを訪れても、明確な印象を残せないままユーザーは離脱してしまうでしょう。
ブランディングにおいては、「何をどう伝えるか」を明確にし、それをデザイン・言葉・構成すべてで一貫して表現することが求められます。ブランドの軸が定まっていないと、ユーザーに響くWebサイトにはなりません。
誰に向けて作られているかが分からない
ターゲットを定めずに作られたWebサイトは、「誰に何を届けたいのか」が不明確になりがちです。その結果、内容が広く浅くなり、どのユーザーにも刺さらないサイトになってしまいます。
たとえば、「初心者向けなのか、専門家向けなのか」「法人向けなのか、個人向けなのか」など、ユーザー像に合わせて言葉遣いや情報の深さ、デザイントーンも変える必要があります。
誰に向けているのかが曖昧なままだと、ユーザーが「自分のためのサービスではない」と感じ、すぐに離脱する可能性が高まります。
ブランディング視点でのホームページ制作では、ペルソナを明確にしたうえで、その人が共感し、理解しやすい構成を設計することが極めて重要です。
見た目だけに注力してしまう「自己満足型サイト」
表面的なデザインにこだわりすぎた結果、ユーザー視点が欠落した「自己満足型サイト」になってしまうケースもよく見られます。
スタイリッシュなレイアウトやアニメーションを多用していても、使いにくかったり、目的の情報にたどり着けなかったりしては、意味がありません。
また、社内の好みや上層部の意見ばかりを優先してしまうと、ブランドとしてどう見られたいかよりも「見せたいこと」を詰め込んだ構成になり、ユーザーとのズレが生じます。
本来のブランディングとは、ユーザーとの接点すべてを通じて、信頼や共感を築くことです。
見た目の“かっこよさ”だけに注力するのではなく、「どのように見られるべきか」「どう感じてもらいたいか」を軸に設計されたWebサイトこそが、ブランド価値を伝えるツールになります。
03 ブランディング視点で見るWebサイトの要素設計
一貫したビジュアルとトーンで「世界観」をつくる
Webサイトにおけるブランディングでは、視覚表現の一貫性がとても重要です。色使い・フォント・写真のトーン・余白の取り方など、すべてがブランドの「世界観」を形づくります。
たとえば、やさしさや信頼感を伝えたいブランドがビビッドな色合いを多用していては、ユーザーとの認識にズレが生じてしまいます。
また、ビジュアルと同様に、言葉のトーンや語り口調の統一も欠かせません。丁寧な敬語で語るのか、カジュアルで親しみのある表現にするのか、ブランドの価値観に合ったトーンを明確にすることで、ユーザーとの接点すべてに一貫性が生まれます。
このように、見た瞬間に「このブランドらしい」と感じてもらえることが、ブランディング視点でのWebサイト設計における理想です。
ターゲットごとの導線・コンテンツ戦略を組み立てる
どんなにデザインや世界観が洗練されていても、ユーザーが目的の情報にたどり着けなければ意味がありません。
ブランディングされたWebサイトでは、ただ情報を並べるのではなく、ユーザーのニーズや行動フローを踏まえた導線設計が求められます。
たとえば、「初めて訪れる人」と「資料請求を検討している人」では、求めている情報が異なります。これらのユーザーに対して、それぞれに適した情報を提供し、次のアクションへスムーズに誘導する必要があります。
また、SEOを意識したコンテンツ設計も重要です。ユーザーの検索意図に沿ったコンテンツを用意し、ターゲットユーザーの行動に寄り添った流れでページ構成を設計することが、ブランディングされたWebサイトの土台になります。
コアメッセージを起点にしたページ構成
Webサイト全体を通じて伝えるべきもの、それがブランドの「コアメッセージ」です。
このメッセージが明確になっていないと、どれだけデザインや機能が整っていても、ユーザーには何も残りません。
コアメッセージとは、ブランドの理念や価値、サービスを通して実現したいことを、端的に言語化したものです。これをページの冒頭や導線の要所に据えることで、サイト全体の軸がブレなくなります。
また、各ページがそのメッセージを補強する役割を担っていれば、ユーザーがWebサイトを回遊する中で自然とブランドの考えに共感し、納得感を持って行動に移せるようになります。
ブランディング視点でのホームページ制作では、この「コアメッセージ起点」の構成が、ユーザーとの信頼関係を築くうえで非常に重要です。
04 「伝える」から「伝わる」へ:Webサイトでブランド体験を設計する
感情に訴えるコピーやストーリーの活用
ブランディングされたWebサイトにおいては、機能的な情報だけでなく、ユーザーの感情に響く表現が重要です。そのために効果的なのが、ストーリー性のあるコピーライティングや、実体験をもとにしたブランドストーリーの活用です。
たとえば、単に「高品質な素材を使っています」と伝えるのではなく、「なぜその素材にこだわるのか」「どのような思いで商品を開発しているのか」といった背景にある想いを語ることで、共感や信頼が生まれます。
また、感情を動かすコピーは記憶にも残りやすく、ブランドイメージの定着にもつながります。数字やスペックだけでなく、人の感情を動かす“物語性”を取り入れることが、伝わるWebサイト設計の鍵となります。
UXとデザインの調和がブランドの信頼感を生む
どれだけメッセージ性の高い内容を盛り込んでも、ユーザー体験(UX)が悪ければ、その価値は伝わりません。
ページが読み込みにくい、ナビゲーションが分かりにくい、スマホで見づらい――そんな状態では、せっかくのブランド設計も台無しです。
ブランディング視点では、デザインとUXは表裏一体です。美しいデザインはブランドの印象を強める一方で、UXはその印象を維持し、信頼へと変える役割を果たします。
たとえば、「やさしさ」を表現するブランドであれば、ゆったりとした余白、落ち着いた動線設計、丁寧な言葉づかいなどが必要です。それらが一貫して設計されてこそ、“体験としてのブランディング”が完成するのです。
具体的な行動につなげるCTA設計もブランディングの一部
ブランディングはイメージや世界観だけにとどまらず、ユーザーの行動につなげる設計まで含めて成立します。
その中でも重要なのが、CTA(Call To Action)の設計です。どこで、どのように、どんな言葉で行動を促すのかは、ブランド体験の一部です。
たとえば、高級感を打ち出したブランドであれば、「今すぐ申し込む!」という表現よりも、「まずは資料をご覧ください」「ご相談はお気軽に」といった丁寧で落ち着いたトーンがマッチします。
また、CTAボタンのデザインや配置場所も、ユーザーの目線や行動心理を意識して設計する必要があります。コンバージョンを高める設計と、ブランドの信頼感を保つ表現は、決して相反するものではありません。
むしろ、「このブランドに行動を促されたなら安心できる」と感じさせることが、ブランディングがしっかり機能している証なのです。
05 ブランディングを軸にしたホームページ制作の進め方
初期ヒアリングで「ブランドの軸」を言語化する
ブランディング視点でWebサイトを制作する第一歩は、ブランドの軸を明確に言語化することです。「何をしている会社か」ではなく、「どんな価値を提供している会社か」という視点が重要になります。
そのためには、制作前のヒアリング段階で、企業の理念やビジョン、他社との違い、顧客から選ばれる理由などを深掘りする必要があります。この段階で軸が曖昧なまま制作に進んでしまうと、後からの調整が難しくなり、伝えたいことがぶれてしまいます。
ブランドの本質を明確にすることで、デザイン・言葉・構成のすべてに一貫性を持たせたホームページ設計が可能になります。これは、結果的にターゲットユーザーの共感を得やすくし、成果にもつながる重要なプロセスです。
サイト設計とデザインを一貫して考える
ブランドの世界観を正しく伝えるためには、情報設計(サイトマップやページ構成)とデザインを一体で考えることが不可欠です。
よくある失敗として、「構成は決まってからデザインを考える」といった分業的な進め方がありますが、それではブランディングの一貫性が崩れてしまうリスクがあります。
たとえば、ブランドが「やさしさ」「安心感」を大切にしているなら、ナビゲーションや導線もそれにふさわしく設計されるべきですし、表現するコピーや色使いもそれに合わせる必要があります。
つまり、構成=情報の流れ/デザイン=印象と感情の流れを合わせて組み立てることで、ブランド体験が自然に伝わるWebサイトが実現します。表層のデザインだけでなく、「設計そのもの」がブランドを体現していることが理想です。
制作後もブランドを育てるコンテンツ運用を視野に入れる
ホームページは「作って終わり」ではありません。むしろ公開してからがブランディングの本番です。
制作段階でブランドの軸を明確にしていても、情報が古くなったり発信が止まったりすると、ユーザーとの関係性は次第に薄れていきます。
そこで重要なのが、ブランドを育てていくための継続的なコンテンツ運用です。
たとえば、ブログやコラムで価値観を語る、事例やインタビュー記事でブランドの活動を紹介するなど、ブランドの“息づかい”を感じさせる情報発信が求められます。
さらに、こうした運用はSEOの観点からも有効です。検索される機会が増えることで、ブランドの接触機会も増え、自然とユーザーの認知・信頼につながります。
ブランディングとは「形にすること」で終わりではなく、「継続的に届け続けること」によって完成していくのです。
06 ブランドを伝えるWebサイトとは?
ユーザーの記憶に残る「ブランド体験」を届ける
Webサイトは単なる情報の羅列ではなく、ユーザーにブランドの価値を“体験”として届ける場であるべきです。見た目の美しさや情報の分かりやすさだけでなく、サイトを訪れたときの印象や感情の動きそのものがブランド体験となります。
たとえば、ストーリー性のある構成や、ブランドの価値観がにじみ出るようなコピー、写真、インタラクション。これらが組み合わさることで、「なんとなく良かった」ではなく「このブランドは印象に残った」と感じてもらえるWebサイトになります。
ユーザーの心に残る体験を設計することが、他社との差別化にもつながり、長期的な信頼の基盤となります。
「共感」「信頼」「行動」につながる設計こそがあるべき姿
ブランドを伝えるWebサイトの目的は、「共感」「信頼」そして最終的には「行動」につなげることにあります。見た目が良いだけでは、共感は得られません。情報が多いだけでも、信頼には至りません。設計のすべてが目的に向かって機能してこそ、意味を持つWebサイトになります。
たとえば、ユーザーの課題に寄り添ったコンテンツで共感を得る。実績や事例、メンバー紹介などで信頼感を高める。行動を促すCTAを、ブランドのトーンに合わせて自然に配置する。
これらが連動することで、ただ情報を届けるのではなく、「心を動かし、行動を引き出すWebサイト」が実現します。
これこそが、ブランディング視点で考えるWebサイトの“あるべき姿”です。
AUTHOR:
VOICE
CONTENTS
ホームページ XLV
成功するホームページリニューアルの考え方とは? 会社で押さえるべきポイントと進める際の視点を解説
ホームページ XLV
「会社の印象を変える!ブランディングデザインの理解と実践」
ホームページ XLIV
「大学ブランディング戦略の成功事例5選と実施ステップ」
ホームページ XLIII
「ブランディングにおけるホームページの役割とそのメリット」
ホームページ XLII
「2025年版!福井のホームページ制作会社徹底比較」
ホームページ XLI
「2025年版!SEO対策会社の選び方と特徴を解説」
ホームページ XL
「ホームページ製作費用の全体像と目的別相場をわかりやすく解説【2025年版】」
ホームページ XXXIX
「クリニックのためのホームページ制作ガイド【2025年版】」
ホームページ XXXVIII
LLMOとは
~検索から対話へ、これからのSEOの進化~
ホームページ XXXⅦ
ブランディング視点で見るWebサイトのあるべき姿
ホームページ XXXⅥ
素敵なホームページが意味を持たない理由
ホームページ XXXⅤ
「なぜ反応がない?」ホームページを公開したのにお問い合わせが来ない理由とは
ホームページ XXXⅥ
金沢でホームページ制作を考える|ホームページを「つくる前」に考えておきたい補助金の話
ホームページ XXXⅤ
Webサイト制作を経営戦略の一部として考える|成果につながるサイト設計とは?
ホームページ XXXⅣ
ブランディングを成功させるホームページ制作のポイント
ホームページ XXXⅢ
ホームページリニューアルで企業の成果を最大化する方法
ホームページ XXXⅡ
ホームページのトラフィックを増やすための基本戦略
ホームページ XXXⅠ
ホームページのデザインとブランディングの重要性
ホームページ XXX
モバイルフレンドリーなホームページ制作の重要性と実現方法
ホームページ XX Ⅸ
なぜホームページでブランディング差がつくのか?webサイト制作会社が解説
ホームページ XX Ⅷ
ターゲット市場に最適化したホームページ制作の方法
ホームページ XX Ⅶ
UXデザインでユーザーを惹きつけるホームページ制作
ホームページ XX Ⅵ
ホームページでビジネスを成長させるための戦略
ホームページ XX Ⅴ
ホームページの開設目的と役割
ホームページ XX Ⅳ
パーパスブランディングの重要性:企業のビジョンを具現化するデザイン戦略
ホームページ XX Ⅲ
モバイルファースト時代におけるホームページ制作の重要性
ホームページ XX Ⅱ
デザインと課題解決の融合:企業の本当の価値を引き出すブランディング
ホームページ XX I
デザインの力で価値を可視化する:UI/UXの未来像
ホームページ XX
問い合わせが急増!ホームページで効果的なCTA設置の秘訣
ホームページ ⅩⅨ
ブランディングとECの融合:オンラインビジネスの新たな潮流
ホームページ ⅩVIII
マーケティングから始まるホームページ制作の成功法則
#ホームページ ⅩⅦ
ホームページの集客術 SNSの効果的な活用法
#ホームページ ⅩⅥ
AIの進化と共に変わるホームページ制作:新たな関係性の創造
#ホームページ ⅩⅤ
ホームページと採用:過去の教訓と未来への展望
#ホームページ ⅩⅣ
企業の顔となるホームページ:ブランディング戦略を活かした制作術
ホームページ ⅩIII
ブランディングの核心:ゴールデンサークルを活用した価値の可視化
ホームページ ⅩⅡ
ホームページ制作におけるChatGPTの役割と新時代のSEO戦略
ホームページ ⅩⅠ
ホームページの保守管理とSEO|メンテナンスのSEOへの影響
ホームページ Ⅹ
SEOとGA4|新しいアナリティクス時代の最前線
ホームページ Ⅸ
コンテンツファーストなホームページ制作
ホームページ Ⅷ
効果的なWEBサイト制作のポイント|目的を明確にする理由
ホームページ Ⅶ
金沢でのホームページ制作費用:予算別ガイドと選び方
#ホームページ Ⅵ
SEO対策の種類と詳細:内部対策と外部対策の違いについて
#ホームページ Ⅴ
SEO対策で変わるホームページの可能性:効果的な戦略と実施法
#ホームページ Ⅳ
ユーザビリティとアクセシビリティ Webサイトの新たな標準
#ホームページ Ⅲ
Webサイトのレスポンシブデザイン モバイルフレンドリーの重要性
#ホームページ Ⅱ
ホームページ作成を依頼する前に知っておきたい5つのポイント
#ホームページ Ⅰ